私のブログでは事あるごとに「型式適合認定」を引き合いに出して話をしてきたんですが、
これまで簡単な説明しかしてこなかったので、今回は型式適合認定について深堀りした記事を書いておこうと思います^^
すいません、記事を書きながら書きたいことがどんどん出て来てしまい、結局全部伝えたいことなので全部詰め込んだ結果、上手くまとめきれてない部分もありますが、
私が知っていることを思いのままにすべて語らせて頂こうと思います^^
型式適合認定とは
まず、型式適合認定とは、
住宅の材料や構造などについて事前に認定を受けることによって、個々の住宅の建築確認や検査などを不要にすることができる制度です。
言い換えれば、
同じ部材で同じ設計ルールに基づいて建てるのであれば、予めその安全性に関して認定されているので、個別の構造計算は不要ですよ、という手続き簡略化のためのルールですね。
住宅展示場にある大手ハウスメーカーの住宅の多くは、この「型式適合認定」という制度を採用しています。
(検証したことは無いですが8割方は適合認定だと思われます。)
型式適合認定を取得する意味、メリット
注文住宅における型式適合認定取得の意味は何でしょうか?
ズバリ、
「型式適合認定を取得していれば、構造計算や建築確認を省略できる。」
これに尽きます。
構造計算や建築確認を省略することができれば、
そのための時間と費用(特に人的コスト)を大幅に削減することができますからね。大量に住宅を供給する大手ハウスメーカーにとってはメリットしかありません!
ええ、そうです。
メリットというのはハウスメーカーにとってのメリットです。
昨今の注文住宅は工業化(工場生産)が進み、適合認定のおかげで構造計算や建築確認等の手間も省けているので、我々一般消費者にはプライスダウンというメリットがあって然るべきなんですが、
実際はこの「工業化住宅」が在来工法との差別化というか、ある種のブランディング戦略みたいな感じになってしまっていて、逆に値上がりしてしまっているんですよね^^汗
ということで、
消費者にとってのメリットは・・・、
無いですね。
うーん、何かないかなぁ・・・。
あっ! 検査が無い分、工期が若干短くなることでしょうかw
ちなみに、
役所にとっても建築確認の審査が大幅に減りますし、何か起こってしまったときでも審査をしていなければ責任をハウスメーカーに押し付けることができますからね。
建築確認申請の裏の意味(ホンネ)は、もしもの事態が発生した時は国は関与しないのでHMが自分たちで何とかしてね、ということなんだそうです。
ええ、そうです。
型式適合認定という制度は国にとってもメリットが大きいんです。
不動産業界では三方良しなんて言葉をよく耳にしますが、結局泣きを見るのはいつだって我々一般消費者なんですよね・・・^^汗
制度の裏側を俯瞰して考えてみるといろんなことが見えてきますよね。
型式適合認定は大手ハウスメーカーに都合の良い制度なんです。
だって今や大手ハウスメーカーはスーパーゼネコンよりも規模が大きいですからね。
(スタジアムや超高層ビルのような建築物を建てるよりも民間向けの住宅を建てた方が儲かるってことです。)
当然、法制度立案への発言力も大きいですから、国だってほとんど大手ハウスメーカーの言いなりだと思います。
そりゃそうですよね。研究開発費だってバカになりませんから、民間でやってもらった方が経済合理性があるってもんです。
↑これはマクロ経済学で言うところの比較優位の法則ってやつですが、官民のバランスを間違えるとトンデモナイ事態に陥りますからね、注意が必要です。
構図としてはワクチンビジネスで荒稼ぎするあの大国のメガファーマと一緒ですね。誰も文句を言えないでしょ笑
(↑この例えは我ながら秀逸w 非常に的を射ていると思います。)
さすがに大手ハウスメーカーは日本の企業なので、人命を蔑ろにしてまで利益最大化を目指すってことは無いと思いますが^^
すいません!話が逸れました!(とっとの話はいつも逸れていきますw)
えっと、なんでしたっけ笑
型式適合認定でしたね。
はい、ということで、型式適合認定は大手ハウスメーカーにとってメリットが大きいように設計されているので、
年間数棟を建てる工務店とかが型式適合認定を取得していないのは、その手続の複雑さもありますが、数棟では認定取得に対するスケールメリットが出ないためと言えます。
かく言う私がマイホームを建てた大成建設ハウジングの場合はこのスケールメリットが出ないという理由もあるのかも知れませんが、
私が調べたところによると、
そもそも型式適合認定を取得するというのは、何かあったときに責任を取れるくらいの財務的な体力も必要な訳ですが、そこまで大規模に営業展開している訳ではないので、旧パルコンからパルコンMAXに切り替わったタイミングで型式適合認定をやめて全棟建築確認申請・構造計算実施に切り替えた、ということのようです。
2019年にはダイワハウスの2000棟を超えるアパートと戸建住宅で型式認定違反が判明したという事象がありましたが、よっぽど体力のある会社じゃないとリカバリーも大変ですよね。
型式適合認定のデメリット
メリットの説明が長くなってしまったので、デメリットは手短に行こうかと思います。
ズバリ、型式適合認定のデメリットは、
- 設計の自由度が制限される
- リフォームやリノベーションなどの増改築が難しく、結局、費用が高くなる
- 構造計算や建築確認がされていない
の3点です。
設計の自由度が制限される
想像に難しくないと思いますが、
型式認定は「同じ部材で、同じつくり方」をするのが前提ですから、型式認定を取得した範囲内でしか設計できないことになります。
要するに、
どこのメーカーのどの部材を床材に使って、サッシや玄関ドアはこの中から選んで、開口部の寸法や天井高の設定もといった具合に、全て事前に認定を取得した範囲内でしか選ぶことができないわけです。
そのため、設計の自由度が少なくなってしまうというデメリットがあります。
リフォームやリノベーションなどの増改築が難しく、結局、費用が高くなる
これは増改築のときに気付くことになるので、新築時には案外気付かない人の方が多いかも知れませんね。
ここの部分を知ると、型式適合認定が大手ハウスメーカーの為に設計されているというのがよく分かると思います^^
まず、
型式適合認定の設計ルールである「型式」の資料は、新築を建てたハウスメーカーしか持っておらず、資料の開示を求めても企業秘密として開示を拒否されてしまいます。
なので、型式適合認定の住宅は新築したハウスメーカーしか増改築改修をすることが出来ない仕組みになっているんです。
第一に、そのハウスメーカーにしか工事を依頼できないので、コンペさせることもできませんから、当然費用は高くなりますよね。
第二に、もしそのハウスメーカーが倒産してしまっていたらどうなるんでしょうね・・・。
リスク分散しましょう!って色んなところで言われている時代に、将来の改修・維持管理まで新築時のハウスメーカー1社のみに頼るって、とんでもなくリスク高くないですか^^汗?
構造計算や建築確認がされていない
やはりこれに尽きますね。
建築基準法では、木造は3階建以上から構造計算が必要で、鉄骨造やRC造は全て構造計算や建築確認が必須になっているのですが、
型式適合認定を取得していれば、こういった審査や検査を省略できてしまうため、構造計算や建築確認がされないまま家が建ってしまうんです。
必要な審査や検査がパスされるようになれば、当然、不正も起こりやすくなっていきます。
こういった不正が原因で起きた認定違反といえば、レオパレスや大和ハウスの事案が記憶に新しいですが、そりゃ、起こって当然だったと思いますよ。
自分で書くのも面倒なので適当な記事が無いかなとネットサーフィンして探してみたところ、
ものすごく分かりやすく型式適合認定の不正についてまとめている記事があったので以下にリンクを貼り付けておきますね^^
レオパの不良アパート、病巣は会社のガバナンスだけではない
(~「4号特例」と「型式適合認定」で検査すり抜け~)
不正した本人も悪いけど、不正が起こりやすい制度をそのままにしておく国も国ですよね・・・。
とはいえ、結局のところ、大手ハウスメーカーの方が立場が上なので今後もしばらく型式適合認定は残り続けると思いますので、
これから新築しようとお考えの皆さんはくれぐれもお気を付け下さいね!^^
まだまだ話したいことはいっぱいあるんですが、長くなってしまいましたので、今日のところは一旦ここまでと致しましょう^^
今回は「型式認定とは」についてお話ししましたので、
次回の【思いのままに語る】シリーズでは、現在の大手ハウスメーカーのような超巨大企業が生まれた時代背景を説明した上で、型式適合認定制度ができた理由などを説明したいと思います。
(急にシリーズ化しましたが、たぶん、2~3記事書いて終わると思います^^汗)
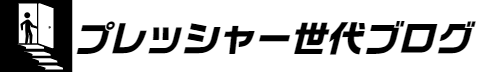

コメント